地元横浜の社労士事務所 残業対策・就業規則・労働(労務)相談・あっせん申請・セミナー
 社会保険労務士小髙事務所 人と企業を前向きに支援します
社会保険労務士小髙事務所 人と企業を前向きに支援します
Social Insurance And Labor Consulting Office
 :045-777-7331
:045-777-7331
 :roumupal@icloud.com
:roumupal@icloud.com


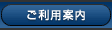
 労働相談 労働相談・転ばぬ先の労働相談 ・ADR代理業務 ・労働問題解決Pack |
 アウトソーシング アウトソーシング・手続代行ネットでGO! |
 顧問契約 顧問契約・運送業の社長さん!労務管理引き 受けます! ・顧問契約 |
 労務コンサルティング 労務コンサルティング・リスクと無駄を見直す就業規則の 作成・変更 ・中小企業の残業代削減対策 ・運送・物流業の就業規則作成 ・みなし残業代制の導入 ・運送業の社長さん!是正勧告引き 受けます! ・運送業の残業時間算定 計ってみ ないと分かりません! ・運送業の賃金制度導入 ・運送業の働き方改革対応プラン |
 転ばぬ先の労働相談室 転ばぬ先の労働相談室 無料労働相談受付中! メール受付、原則24時間以内に 回答致します。 面談随時対応 ・社内解決相談室 ・紛争解決相談室 ・解雇相談室 ・不払い残業相談室 ・セクハラ相談室 |
 人事・労務コンサルティング 人事・労務コンサルティング・就業規則でモラールUP! ・労働時間制度 労働時間とは 法定労働時間と所定労働時間 36協定による時間外・休日労 働と割増賃金 振替休日と代休 管理職と割増賃金 1年単位の変形労働時間制 ・残業対策 ・労務リスクと是正勧告 ・人事制度 賃金制度でモラールUP! 高年齢者でモラールUP! |
 労務コンプライアンス 労務コンプライアンス・労働時間 コンプライアンスとは 不払い残業 管理監督者 過重労働 ・解雇 解雇制限 普通解雇 解雇予告 懲戒解雇 整理解雇 雇止め 内定取り消し ・労働条件 不利益変更 配置転換 職種変更 在籍出向 転籍出向 |
 コラム コラム・名ばかり管理職とリスク管理 ・その派遣切り雇止め、大丈夫です か? ・人件費の変動費化 ・残業をなくす方法 |

| ・みどり社労士会 ・神奈川県社会保険労務士会 ・神奈川県社労士会横浜北支部 ・全日本トラック協会 ・神奈川県トラック協会 |
| 運送業の働き方改革 H29/11/1 |
| 「働き方改革実行計画」により長時間労働の是正を図る観点から、運送業においても時間外労働の罰則付き上限規定が導入されることになり、改正労基法施行の5年後から、年960時間(=月平均80時間以内)の上限規制が適用されることになります。 自動車の運転業務についての見直しにあたってのポイントは以下のとおり。 ①十分な猶予期間の設定 ②段階的実施(年960時間以内の規制で適用開始。将来的には一般則の適用を目指す。) ③長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進
|
|||||||||||

