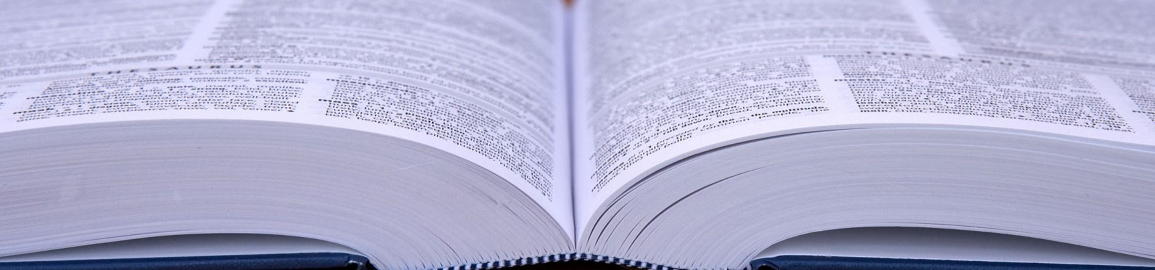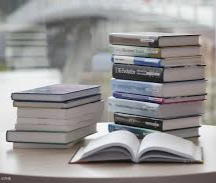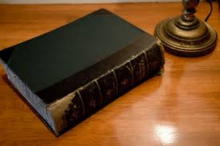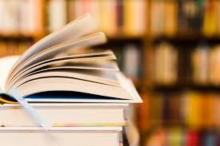| 運送屋さんの労災事故と損害賠償 |
 |
運送業の労災事故を大きく分けてみますと、通勤災害を除くと交通事故と作業中の事故に区分されます。 業務遂行性 業務遂行性労働者が、事業主の指揮命令下に置かれている状態で、負傷したり、病気にかかったりすること。  業務起因性 業務起因性労働者が従事している業務と負傷等の間に客観的な関係が有ること。 労災事故と認定される為には、以上の要件を満たす必要があります。また、労災保険では使用者の無過失責任の考え方をして いますので、例え会社に過失がなくても、一定の責任は会社にあるとされています。 |
さらに、無理な作業指示をしたり、安全配慮義務を怠った作業を行うのが通常であった場合などは、損害賠償責任を負うこととなります。
運送業における運転中の事故及び作業中の事故は、労災事故であることはもちろん、その原因が長時間労働、過重な積荷・積み降ろし、改善基準告示違反、
労基法違反等である場合には、損害賠償責任を問われることになります。逆に運転手が義務を履行しなかったり、故意に又は過失によって会社に損害を与え
た場合にも、損害賠償責任が発生します。
| 損害賠償請求 |
 債務不履行による損害賠償 民法第415条
債務不履行による損害賠償 民法第415条労働契約上の義務を契約上の一方が履行しない場合、又は一方の責任で履行不能となった場合をいいます。
民法415条は、このような債務不履行をした者に対して、損害賠償責任を課しており「債務不履行責任」と言われています。
 不法行為による損害賠償 民法第709条
不法行為による損害賠償 民法第709条故意又は過失によって他人の権利を侵害し、損害を与えた場合は、「不法行為責任」により損害賠償が課せられます。
債務不履行と違い加害者と被害者の間に契約関係がないことが特徴で、交通事故が典型例です。
ただし、契約関係上でも善管注意義違反等の過失により損害を与えた場合に不法行為が発生します。
不法行為責任が認められる為には、以下の要件が必要とされています。
①故意又は過失が認められること
②人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
③その行為により損害が生じたこと(相当因果関係)
④加害者に責任能力が認められること
 使用者責任による損害賠償 民法第715条
使用者責任による損害賠償 民法第715条使用者は、労働者が業務上、第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任があるとされており、これを「使用者責任」と言います。
ただし、使用者はその賠償について、労働者に対して請求することができます。(第3項)
運転手が運送中に事故を起こした場合、事故の被害者は、その会社に対して損害賠償を請求することができるということであり、会社はその負担を直接の
加害者である運転手に請求することができるということです。
■実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、損害額を予め定めておくことは労働基準法違反となります。(労働基準法第16条)
■労働者の同意なく、賃金と損害額を一方的に相殺することは、労働基準法の「賃金全額払い」の原則違反となります。(労働基準法第24条)
 運転手への損害賠償請求
運転手への損害賠償請求運転手(労働者)は、使用者(会社)のために、使用者の指揮命令によって業務遂行しますので、その過程で生じた損害の全てを運転手の責任にすることは
不均衡である為、使用者の運転手に対する損害賠償請求権及び求償権については、全責任ではなく一部責任に制限するという考え方が定着しています。
このような処理は、、使用者と運転手の経済力の差や、運転手が業務を行うことによって利益を得る使用者は、そこから生じるリスクも公平に負担すべき
という考え方から、損害も公平に負担することとされています。
ただし、運転手(労働者)が、故意又は重過失により会社に損害を与えた場合は、全ての損害について運転手(労働者)に請求することができます。
| |
|||||||||

|
|||||||||
| |
|||||||||
 |
|||||||||
|
|
|||||||||
Social Insurance And Labor Consulting Office TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com |

 TEL:045-482-6047
TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com
mail:roumupal@icloud.com