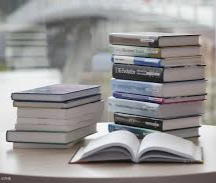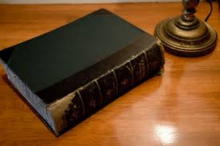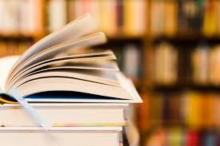| 運送屋さんの同一労働同一賃金 |
 |
運送屋さんの傾向と対策! 労働契約法20条とパート労働法が統一され、パートタイム・有期雇用労働法として改正され、改正労働者派遣法と同時 に2020/4/1に施行されました。 (パートタイム・有期雇用労働法における中小企業については2021/4/1)運送業に及ぼす影響と対策について考えて みましょう。 |
| 労働力不足 |
運送業の人手不足が叫ばれて久しいですが、一般企業同様、その労働力不足と景気の変動に対応する役割を非正規労働者が担っています。
運送業においても非正規労働者の割合は、3割程度あると言われておりますが、中小の運送屋さんの現場では正社員比率が高いように感じております。
労働力不足をパートや有期雇用、派遣労働者によって補うことは、人件費の変動費化と相まって通常業務の中に組み込まれているでしょうし、今後も増加
することが想定されます。
若年層の就業者が増えないなか、非正規、正社員を問わず、女性や高年齢者は貴重な戦力ですし、女性労働者や定年退職者に対する労働環境の整備や均衡・
均等待遇への取組が急務です。
特に年齢構成も高い中小の運送屋さんにとっては、定年後の継続雇用による有期雇用労働者に対する、改正高年齢者雇用安定法による高年齢者就業確保措置
(努力義務)への取組みも含めて重要となります。
| 労働条件 |
運送業の労働力不足の原因の一つに、賃金を含む労働環境があげられます。低賃金、長時間労働は運送業の代名詞になっています。
2023/4/1からは、中小企業も60H超の残業の場合に、割増率が50%以上の率で計算した割増賃金を支払うことになっております。
さらに翌年の2024/4/1からは、労働時間の上限規制が猶予されていたドライバーも上限規制が始まります。
一般の業種と違い年間960Hの総量規制のみとはいえ、今までのように青天井で時間外労働をしていると、最後にとんでもないことになりかねません。
賃金と労働時間は表裏一体で、ドライバーの労働条件を考えるのには、この二つを切り離して考えることはできません。
「同一労働同一賃金」については、正社員とパートや有期雇用労働者、定年後の継続雇用労働者、無期転換労働者などとの労働条件をどうするのか。
均等・均衡待遇を確保する為の、「職務内容」や「職務内容・配置の変更」等の労働条件をどうするのか。やることが“てんこ盛り”で、どこから手を付け
たらいいのか考え込んでしまいますが、時間は待ってくれません。まずは、現状を把握し、御社の将来を見据えて順序良く取り組みましょう。
 |
職務内容、職務内容と配置の変更内容、その他の事情 同一労働同一賃金は、働き方改革の一環として正社員(無期フルタイム労働者)と非正規労働者(有期、パート、派遣労働者) との不合理な待遇さの禁止をするものですが、同一労働同一賃金といっても必ず正社員と同じ賃金を払わねければならないと いう訳ではなく、職務内容や異動の有無や転勤の範囲等の違いに応じて判断され、賃金についても基本給や各手当ごとに判断 されます。 |
均衡待遇 |
均等待遇 |
| (不合理な待遇の禁止) パート・有期雇用労働法第8条 派遣法第30条の3 ①職務内容(業務内容+責任程度) ②職務内容・配置変更の範囲、 ③その他の事情に相違がある場合 違いに応じた賃金(違いに応じた格差は可) |
(差別的取り扱いの禁止) パート・有期雇用労働法第9条 派遣法第30条の3第2項 ①職務内容(業務内容+責任度) ②職務内容・配置変更の範囲が同じ場合は同一賃金 |
職務の内容 |
|
業務内容 |
責任の程度 |
| 職業分類細分表より (例) ・トラック運転手 ・トレーラートラック運転手 ・タンクローリー運転手 ・倉庫作業員 ・FL運転作業員 |
①権限の範囲 ②業務成果の役割と期待度 ③緊急時対応の程度 ④所定外労働の頻度 |
職務の内容・配置変更の範囲 |
|
| ・転勤の有無と範囲(エリア内、全国) ・職務・配置変更の有無と範囲 |
|
正社員とパート・有期雇用労働者との間で、上記の内容に違いがあれば違いに応じて「均衡待遇」とし、同じであれば「均等待遇」として待遇に差をつけては
いけません。
| 均衡待遇と均等待遇 |
ここでは、「均衡」と「均等」の違いを整理してみます。
均等とは正社員と職務内容等が同じで正社員と=(イコール)ということですから、正社員と同一の賃金を支給することになります。
一方、「均衡」とは、職務内容等が正社員と違う程度によって、=(バランス)をとって賃金を決めることになります。
パートタイム・有期雇用労働法第8条では、均衡待遇について「当該待遇を行なう目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違
を設けてはならない。とされておりますが、均衡待遇による待遇差については、内容や理由を説明できるようにしておく義務があります。
 |
均衡・均等と説明義務対応 パート・有期労働法で事業主に求められることは、一つは正社員とパートや有期労働者との不合理な待遇差の禁止であり、 二つ目は待遇差がある場合の説明義務です。 これを法令に則って実施するためには、まず、自社の状況を把握する必要があります。 その結果、不合理な待遇差と判断される場合や判断される可能性がある場合には、待遇差の改善に取り組む必要がありますので、 従業員の雇用形態や労働条件を確認して、不合理の有無や内容、理由を整理することから始めましょう。 |
| 均衡・均等待遇対応 |
正社員と有期雇用フルタイム、パート、定年継続雇用等の雇用形態別に職務や労働条件を整理して、正社員の働き方や役割との違いに見合ったバランスの
とれた「不合理な待遇」ではないことを確認し、不合理ではないことの理由も整理しておく必要があります。
もし、その待遇差の理由が明らかでなかったり、明らかに不合理な場合には、改善措置を講ずる必要があります。
| 均衡・均等待遇対応 |
パート・有期労働法第14条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)により労働者に対する待遇に関する説明義務が強化されました。
パート・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。事業主は、パート・
有期労働社から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
【雇い入れ時の説明】
パート・有期労働法第8条~13条
・均衡・均等待遇について
・賃金の決定方法
・教育訓練・福利厚生施設の利用に対する均衡・均等待遇
・通常の労働者への転換措置
【説明の求めがあった場合】
・正社員との待遇差の有無
・正社員との待遇差の内容と理由について
(「職務内容」及び「職務内容・配置変更の範囲」、「その他の事情」について)
| |
|||||||||

|
|||||||||
| |
|||||||||
 |
|||||||||
|
|
|||||||||
Social Insurance And Labor Consulting Office TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com |

 TEL:045-482-6047
TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com
mail:roumupal@icloud.com