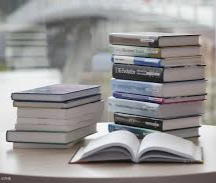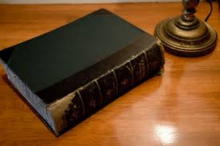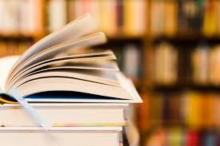| 解雇のコンプライアンス -普通解雇・懲戒解雇・整理解雇・休職解雇・雇止め- |
 |
民法上解雇は、辞職と同等に取り扱われており、雇用契約の解約は労使双方から、いつでも自由に解約できるものとされています。 そしてその申入れは2週間で成立します。(民法627条) しかし、事業主からの解雇は、従業員の生活に大きな影響を及ぼす為、いくつかの解雇制限の規定があります |
 労働契約法第16条 解雇権濫用法理
労働契約法第16条 解雇権濫用法理
解雇理由や解雇手続に対する制限。
労契法第16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」とされてい
ます。ということは、客観的合理的理由があり、かつ、その理由が社会通念上相当な程度なければ、解雇権濫用で無効になるということです。
では、客観的合理的理由とは何なのでしょうか。
労働契約も契約ですから、その契約内容である業務を遂行することができない程の能力不足の場合、また、業務に支障をきたすほどの服務規程違反及び懲戒規程に
抵触するような行為の場合が想定されます。さらに、社会通念上相当とは、その程度が労働契約を維持することができないほど重いことが必要になると考えます。
 労働基準法第20条 解雇予告
労働基準法第20条 解雇予告
解雇予告期間と解雇予告手当に関する規定
労基法第20条では、「労働者を解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告、又は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」として
おります。要は、解雇の30日前に解雇予告をすれば、解雇予告手当は必要ありませんし、解雇予告と解雇予告手当を合わせて、30日以上になれば良いと言うこと
です。例えば、10日分の平均賃金を支払えば、20日前の解雇予告で足りるというように、予告日数を短縮することできます。
解雇日については、少なくとも30日前とされていますので、30日以上前であれば40日前でも50日前でも構いませんが、「○月○日の終了をもって解雇する」と
いうように、解雇日を特定する必要があります。そしてその翌日が解雇の効力発生日となります。
解雇予告日と解雇の効力発生日との間に暦日で30日以上の日数が必要だということです。
 労働基準法第19条 解雇制限
労働基準法第19条 解雇制限
●業務災害の療養期間中とその後の30日間の解雇禁止
●産前産後休業期間とその後の30日間の解雇禁止
この期間中に解雇することは禁止ですが、制限期間満了後に解雇する為に解雇予告をすることは可能です。
 差別的解雇の禁止
差別的解雇の禁止
●国籍・身上・社会的身分による差別による解雇禁止
●労働者が女性であることを理由とする解雇禁止
●不当労働行為による解雇
 |
休職とは、従業員が私傷病(業務外の傷病)により就労できない場合に、会社がその従業員との労働契約を維持しながら労務の提供を 免除又は禁止することを言います。 また、休職制度を設けた場合には、労働条件として明示する必要がありますし、(労基法第15条、労基法施行規則第5条1項11号) 就業規則の相対的必要記載事項として就業規則に規定しておかなければなりません。(労基法第89条) |
労働契約上、労務の提供ができなければ債務不履行として普通解雇が想定されるところですが、休職制度はこれを一定期間猶予して普通解雇の有効性の判断に
伴う社会的相当性が成立するための要因としての意味を持っているとされています。
要は解雇問題が発生した場合に解雇の成立要因の一つに成りうるとされているということです。
| 休職後の退職・復職 と合意退職 |
以前の就業規則における「休職規定」は、期間満了しても復職できない(治癒しない)ときは、期間満了の日をもって解雇とする。という規定が多かった為、解雇
問題に発展するケースが散見され、最近では殆どの就業規則が期間満了による退職といった自然退職に改められていますが、治癒の判断基準につきましては、
トラブル回避のためにもさらに具体的に規定しておくべきでしょう。
例えば、「治癒とは従前の業務を通常程度に遂行できる程度に回復している状態」とします。それでもメンタル休職については、自然退職といっても不当だと訴え
られたり、復職すれば再発問題となったりすることもまれではありませんので、さらに具体的な基準を規定することも検討すべきでしょう。
復職してもすぐに従前の仕事に就く程には回復していないが、より軽易な業務なら就くことができ、本人もそれを希望しているような場合であっても、中小企業で
はそれに対応できる職種が存在するとは限りませんし、運送業のドライバーのような実態として職種限定の業務従事者については新たな業務を作ってまで対応する
必要はないと考えます。
従来の業務に従事できないのであれば、休職後の対応によっては労働問題に発展する可能性もありますし、傷病を克服して体調を戻してから従業員の再出発を図る
といった意味でも、休職中又は休職後の合意退職の検討も一考かと考えます。
その際には、会社都合扱いとして退職金等にも一定の配慮をすることも大切ではないでしょうか。
| 休職後の退職・復職 と合意退職 |
メンタルヘルス疾患により休職・復職を繰り返す社員がいます。
復職しても通算規定の範囲を超えると欠勤し始め、休職の算定期間である労務不能日数を超えると休職を要求されたりします。
要は、休職規定どおりに欠勤し、労務不能となり、休職し、復職し、一定期間をおいてまた、欠勤を繰り返すということになります。
本来、規定上休職を決定・命令するのは会社なのですが、就業規則上の権利として要求されたりします。従業員としては、期間満了になると自然退職になる可能性
があるため無理に復職するケースもあるでしょうが、会社としては規定通りの対応が必要となりますし、制度上の問題はないため、会社としては難しい対応を迫ら
れます。では、そのような社員を解雇することはできないのでしょうか。
通常、治癒の判断は期間満了時に行なわれますが、何らかの理由で新たな休職期間に入ってしまった場合でも、常に期間満了時でなければその判断ができないのか
という問題が発生します。何故ならば休職期間の本質は、一定の休職期間、退職・解雇を猶予し回復するための時間を与えることにあるからです。
複数回の休職を繰り返した従業員については、既定の休職期間を既に消化してしまった場合もあり、それだけでも労働契約上の債務不履行に該当すると考えます
が、当然ながら、休職期間中の労務不能(普通解雇)の判断につきましては、主治医や会社の指定医(産業医)の意見を踏まえて慎重に行なうべきでしょう。
できれば、最後の欠勤が始まった休職期間前が有効なのではないかと私としては考えています。
 |
普通解雇とは、従業員が労働契約に伴う債務を履行することができない場合に、使用者からの労働契約の解消を言います。 従業員側の理由とは、能力不足とか、服務規定や普通解雇規定又は懲戒規程に抵触するような企業秩序違反があげられます。 ただし、使用者の都合だけで簡単に従業員を解雇することはできまん。前述しましたように解雇権の濫用(労働契約法第16条)と みなされた場合には無効となります。 また、労働基準法第89条は、就業規則作成義務を負う企業に対して、「退職に関する事項」として「解雇事由」の記載を義務付け ており、あらかじめ規定されていない解雇理由では、原則として解雇できません。 ただし、現実的には就業規則の解雇事由の中に「その他前各号に準ずる場合」等の包括条項を含むことが多く、その場合は、解雇 理由を解雇権濫用法理の下で総合的に判断されることになります。 |
| 普通解雇要件 |
 就業規則の解雇事由に該当するか否か(包括事由含む)
就業規則の解雇事由に該当するか否か(包括事由含む)
労基法89条3号の「退職に関する事項」は就業規則の絶対的必要記載事項とされ、「解雇の事由を含む」と明記されておりますので、解雇事由も就業規則に規定
する必要があります。
 解雇理由の合理性
解雇理由の合理性
①能力不足
②私傷病による労務の債務不履行
③勤務態度不良
④企業秩序違反
⑤事業の縮小又は廃止(整理解雇)
 解雇の社会的相当性
解雇の社会的相当性
●社会的に解雇してもやむを得ないと判断されること
●解雇回避努力を尽くしたかどうか
※能力不足の相当性
客観的評価によるものとされ、かつ、社会的通念に照らして行う。
相対的評価は常に一定の下位者が存在するため認められない。
 解雇予告と解雇予告手当の支払
解雇予告と解雇予告手当の支払
解雇予告は、「解雇予告通知書」又は「解雇通知書」として書面で伝えることが後々のトラブル防止のために大切です。又、解雇予告手当は、解雇の申し渡しと
同時に通貨で直接支払わなければなりません。
①解雇予告の除外
天災事変その他やむを得ない事由の為、又は労働者の責めに帰すべき事由がある場合には、予め労基署長の認定を受けることにより、解雇予告も予告手当の支払い
をせずに労働者を即時解雇できる。ただし、「天災事変その他やむを得ない事由」とは、何をもってしても事業の継続が不可能な状況であることであり、「労働者の
責めに帰すべき事由がある場合」とは、懲戒解雇事由相当の重大で悪質な行為があった場合とされていますので、除外認定のハードルは結構高いと思われます。
②解雇予告の例外
臨時的・短期的な労働者については、その期間・内容により一定期間を超えて使用されない限り、即時解雇の対象となります。ただし、業務上負傷し休業した場合
には解雇制限の対象となり即時解雇はできなくなります。
一方、契約期間の満了は、原則として解雇ではありませんので、解雇制限期間中であっても所定の契約期間が満了したときは、労働契約を終了させることができ
ます。
解雇予告の適用除外 |
解雇予告が必要となる場合 |
| ①日々雇い入れられる者 | 1ヶ月を超えて引き続き使用された場合 |
| ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用された場合 |
| ③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 | |
| 試みの試用期間中の者 | 14日を超えて引き続き使用された場合 |
臨時的・短期的な労働者については、その期間・内容により一定期間を超えて使用されない限り、即時解雇の対象となります。ただし、業務上負傷し休業した場合
には解雇制限の対象となり即時解雇はできなくなります。
一方、契約期間の満了は、原則として解雇ではありませんので、解雇制限期間中であっても所定の契約期間が満了したときは、労働契約を終了させることができ
ます。
 |
懲戒解雇は、重大な企業秩序違反をした者に対して課す制裁としては最も重い懲戒処分で、諭旨解雇とともに企業外に放出することを前提 とした処分です。 解雇権濫用法理の適用を受けますし、普通解雇のように債務不履行による労働契約の解消ではなく、制裁としての解雇が認められる程度の 事由が必要となります。また、手続的には解雇予告も解雇予告手当も必要ですし、上記「普通解雇」の4.に記載しましたように、解雇予告 を除外するには、「労働者の責めに帰すべき事由」かつ、行政官庁の認定が必要となります。 重大な懲戒解雇事由があったとしても、会社の意思だけで「即日解雇」できるわけではありません。 |
| 懲戒解雇要件 |
 労働者の行為及び態様(労契法15条 懲戒)
労働者の行為及び態様(労契法15条 懲戒)
労働者を懲戒する場合は、当該懲戒行為の性質及び態様が、重大かつ悪質であることが必要です。
例えば、無断欠勤14日以上や他の従業員に対するパワハラ違反による暴行・脅迫、金銭の横領等の重大な企業秩序違反行為があげられます。要は、労働関係から
排除する程度の事実関係が必要となります。
 労働者の行為が就業規則の懲戒解雇規定に該当すること
労働者の行為が就業規則の懲戒解雇規定に該当すること
懲戒解雇事由は、限定列挙とされ、その事由が就業規則の懲戒解雇規定に明記されている必要がります。
 解雇権濫用法理の適用(労契法16条 解雇)
解雇権濫用法理の適用(労契法16条 解雇)
解雇は、客観的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
①客観的合理的理由
・労働者の行為が就業規則の懲戒解雇規定に該当し、かつ、その程度が懲戒解雇に値する事実が認められるか否か
・解雇しないと企業の運営に支障をきたす程度の必要性
・労働者に弁明の機会を与えているか
②社会的相当性(懲戒行為の性質及び態様)
・社会的判断による罪と罰のバランス
・社会的に解雇が相当と判断されること
・故意又は重過失の原因、程度
・会社に対する今までの貢献度と会社が受けた損害の程度
・行為後の反省の程度
これらを総合的に判断することになります。
 解雇予告と解雇予告手当の支払(労基法20条)
解雇予告と解雇予告手当の支払(労基法20条)
解雇予告と解雇予告手当は、普通解雇と同様ですが、懲戒解雇事由の内容によっては労基署の除外認定により即時解雇が可能となります。
ただ、労基法20条但し書きの「労働者の責めに帰すべき事由」とは、通達により内容が決まっており、就業規則における労働者の解雇事由と必ずしも一致しない
可能性がありますので注意が必要です。
 |
整理解雇とは、事業の縮小、廃止、合理化等による人員の整理に伴う解雇のことで、就業規則上は普通解雇に属し、労働者の責めに帰 すべき事由もないのに、会社から一方的に労働契約を解除をされることを言います。 民法では、労働契約の解約は労使ともにいつでもできるとされておりますが、判例や労契法16条に規定されました解雇権の濫用規定に より、大きく制限されています。 さらに、整理解雇においては、昭和50年代以降「整理解雇の4要件」を満たす必要があるというのが優勢でしたが、その後、4つの要 件はその整理解雇が権利の濫用に当たるかどうの判断要素であって、事案ごとの事情を総合評価して判断するという、東京地裁の判例 により整理解雇が認められ易い傾向にあり、その厳格性は薄らいできているようです。 ただ、4要件又は4要素が判断基準であることには違いはありませんので、要件に沿って手続を進めていく必要があります。 |
| 懲戒解雇要件 |
 人員整理の必要性
人員整理の必要性
必要性の程度と内容は企業により様々でしょう。可及的速やかに人員整理をしなければならない企業もあるでしょうし、近い将来の為とか、経営的に余裕が欲しい
と考える経営者もいるかもしれません。
判例では、倒産必至という状況までは要求されていないようですが、余剰人員が発生しているのが最低条件であり、配転や一時帰休の解雇回避が難しい等の経営上
の合理的理由が必要です。また、必要性の程度が低い場合は、解雇回避の圧力が強くなるという指摘もあります。
例えば、大企業と中小企業、製造業と運送業、IT関連企業では、同じ基準で判断することは難しく、企業の規模や業種、経営状況によって各企業ごとに必要性が判
断されることになります。
 解雇回避努力
解雇回避努力
解雇回避努力については、人員整理の目的を達っすることができる解雇回避の方法があり、その方法が容易である場合には、その手段を講ずべき信義則上の義務が
あるとした判例があるように、企業規模、経営状態、従業員構成等により、解雇回避の実施が必要となります。
一般的には、①経費削減 → ②時間外労働の削減 → ③新規採用の中止 → ④昇給中止・賞与削減 → ⑤配置転換・出向等 → ⑥一時帰休 →
⑦非正規社員の契約解除 → ⑧希望退職者の募集となります。
また、④以降の間には、役員報酬の削減も必要かもしれません。
ただし、体力のある大企業と100人以下の中小企業を一律に考えることはできません。ちなみに、社労士の顧客である企業は、中小企業がほとんどであります
ので、上記の内容でもできることは限られてきます。
①の経費削減については、すでに経費は抑えるだけ抑えているでしょうし、④の昇給なんて元々ないし、賞与もなかったり、気持ち程度だし、⑤の配置転換する
部署なんてあるわけないし、⑥の一時帰休させて休業手当を支払う余裕があれば、整理解雇なんてするわけないし、なんていうことになるかもしれません。
特に30人以下の零細企業さんであればなおさらでしょう。
(該当しない企業さん、すいません。でも、該当しない企業さんは、もともと整理解雇のページなんて見ないかな)
では、どうしましょう。上記の①~⑦のすべてをすることは、経営実態として無理かもしれませんが、整理解雇を回避するために最善を尽くし、やむを得ないと判
断される程度の経営努力が必要となります。
 解雇対象者選定の合理性
解雇対象者選定の合理性
整理解雇は、従業員の中から解雇対象者を選定しなければなりません。その選定にあたっては、その従業員の将来にきな影響を及ぼすため、合理的基準の設定と運
用が必要です。
例えば、
①企業貢献度 能力や過去の勤務成績を含め、今後の企業再建への貢献度を含めて検討
②家庭への被害の少ない者 教育費や介護費がかかる者は被害が大きく、独身や共稼ぎの者は低いと判断。
③帰属性 企業への帰属性が薄い、パートや有期労働者等の非正規労働者の削減
このような基準を設定し、公平に運用することが大切です。
正社員は、一般には非正規労働者より先に解雇されることは、ないと考えられますが、固定費の削減が喫緊の課題の企業にとっては、人件費の高い正社員を先に
解雇対象としたケースが有効とされた判例もあります。
 手続の妥当性
手続の妥当性
会社は、労組又は従業員に対し整理解雇の必要性や具体的内容(時期・規模・方法)について十分に説明、する信義則上の義務があります。この手順を踏まない
整理解雇は認められません。
上記のように、整理解雇の有効性を判断するには、企業規模や雇用形態により、できることとできなことはありますが、大きな項目としてはしっかり実施する必要
があります。
 |
雇止めとは、解雇権濫用法理の確立により、解雇が難しくなった正社員に代わる雇用の調整弁として雇用されることになった有期労働 者の契約が、反復更新されているうちに手続が形骸化して、期間の定めのない労働契約と変わらない状態となっているにも拘わらず、 会社が一方的に更新拒絶の意思表示をすることを言います。 さらに、更新手続きがしっかりしていても、契約更新による長期雇用を期待させる言質を与えているような場合にも、判例(東芝柳町 工場事件S49/7/22・日立メディコ事件S61/12/)により解雇権濫用法がる類推適用されるとの判断が示されており、現在では、こ れが労契法19条に規定され法定化されています。 |
平成30年からは、平成25年以降に有期労働契約を締結した、有期労働者が無期労働契約への転換を申し入れすることができる無期転換ルールが実施されています。
無期転換ルールは、通算5年目を超えて契約する者が、6年目の契約以降に申込できる権利が発生することを言います。申し込みをされると会社は原則拒否できませ
ん。ただ、むやみに雇止めをして、人材不足のおり雇止め法理である労契法19条を適用されてもメリットがあるとは思えません。
労務管理上、正社員とのバランスを検討して、無期転換社員としての労働条件を確立するのも必要かと考えます。
| 有期労働契約の締結・更新雇止めに関する基準 |
 雇止め予告
雇止め予告
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当
該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予
告をしなければなりません。
雇止め予告が必要となる場合 |
|
① |
有期労働契約が3回以上更新されている場合1 |
② |
1年以下の契約期間の有期労働契約が更新又は反復更新され、最初に有 期労働契約を継続してから通算1年を超える場合 |
③ |
1年を超える契約期間の労働契約を締結した場合1 |
 雇止め理由の明示
雇止め理由の明示
使用者は、雇止め予告後に労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
雇止めが実行された後においても、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
尚、明示すべき理由は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。
(例)
・前回の契約更新時に、更新しないことが合意されていたため
・契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、その上限に係るものであるため
・担当業務が終了・中止したため
・事業縮小のため
・業務を遂行する能力が十分でないと認められるため
・職務命令に対する違反行為をおこなったこと、無断欠勤等の勤務不良のため
 契約期間についての配慮
契約期間についての配慮
使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及び当該労働者の希望
に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
 1回の契約期間の上限(労基法14条対応)
1回の契約期間の上限(労基法14条対応)
有期労働契約の1回の契約期間の上限は原則3年となっており、例外として
①高度の専門知識を有する労働者との労働契約 → 1回の契約期間の上限5年
②満60歳以上の労働者との労働契約 → 1回の契約期間の上限5年
③一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 → その期間
| |
|||||||||

|
|||||||||
| |
|||||||||
 |
|||||||||
|
|
|||||||||
Social Insurance And Labor Consulting Office TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com |

 TEL:045-482-6047
TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com
mail:roumupal@icloud.com