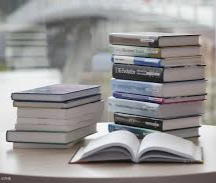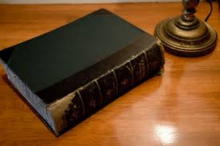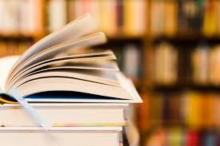| 個別労働紛争解決システム |
 |
昨今の経営環境の変化のなかで、就業形態の多様化が進み、人事・労務管理の個別化が進むことにより、個々の労働者と経営者との間の 個別労働紛争が増加しております。 ADRとは「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判によらないで当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの 手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。 こうした個別労働関係紛争に関するADRの申し立ては、本人が直接行うことができますが、「特定社会保険労務士」に代理人を頼むこと もできます。会社側(経営者)と個人(労働者)、双方が裁判に必要な時間や費用をムダにすることなく、スピーディに柔軟な解決策へ と導くことを主な目的としています。 |
だまって定年まで我慢するか即退職しますか?
それとも泣き寝入りしますか?
はたまた酒飲んで暴れますか?
どれもあまり良い解決にはなりそうもありません。そんなときは、「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。
それがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
トラブルの円満解決を一緒に目指しましょう。
| 個別労働紛争解決システム |
個別労働紛争解決促進法が施行され、次の公的制度が利用できます。
 ワンストップサービスとしての総合労働相談コーナー
ワンストップサービスとしての総合労働相談コーナー都道府県労働局長は、個別労働紛争の未然防止と自主的な解決の促進の為、労働者や事業主に対して情報の提供、相談その他の援助を行う。
これを行うのが総合労働相談コーナーで、ワンストップサービスとしての機能を果たし、労働関係の相談を広く受けつけているが、労働法の法令違反と見られる
事案は、所轄の行政機関(労基署・職安・均等室)の処理に委ねることになります。
 都道府県労働局長の助言・指導
都道府県労働局長の助言・指導民事上の個別労働紛争について、当事者の一方又は双方から解決の為の援助を求められた場合、紛争当事者に対して法令や判例等を照らして個別労働紛争の問題点
を指摘し、必要な助言又は指導をすることができる。
例えば、解雇された労働者から申請があった場合、都道府県労働局長は、その解雇が解雇権濫用にあたるおそれがあると判断した場合は、解雇を撤回したり再考
するよう助言・指導を行うことができます。
 紛争調整委員会のあっせん
紛争調整委員会のあっせん紛争調整委員会により指名されるあっせん委員が当事者の間に立って、話し合いを促進することを目的とする非公開の調整手続です。
ただし、あっせんは当事者の合意に基づく紛争解決手続であり、相手が手続に参加する意思がない場合には手続は打ち切られます。
【あっせんの特徴】
①あっせんを受けること自体には費用はかかりません。
②合意の効力は、民法上の和解契約の効力をもちます。
③非公開の為、プライバシーを保護します。
④あっせん申請による労働者への不利益取扱いは法律により禁止されています。
| あっせん・調停の代理 |
 都道府県労働局のあっせん代理
都道府県労働局のあっせん代理個別労働紛争解決促進法に基づき都道府県労働局(紛争調整委員会)が行うあっせん手続について紛争の当事者を代理すること。
【あっせん対象となる紛争】
原則として労働基準法違反とならない民事上の個別労働紛争で、募集・採用を除くものが対象
●解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
●いじめ、嫌がらせ、パワハラ、セクハラ等の職場環境に関する紛争
●会社分割による労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争● その他、退職に伴う研修費用の返還、営業者等会社所有物の破損に係わる
損害賠償をめぐる紛争
 都道府県労働委員会のあっせん代理
都道府県労働委員会のあっせん代理都道府県労働委員会が行う個別労働紛争に関するあっせん手続について紛争の当事者を代理すること。
道府県労働委員会の場合、本来は労働関係調整法による労働争議の斡旋を実施するところですが、その延長上により、個別労働紛争のあっせんも行っています。
 社労士会労働紛争解決センターでのあっせん代理
社労士会労働紛争解決センターでのあっせん代理ADR法による厚生労働大臣の指定を受けて個別労働紛争を解決する民間のあっせん機関である解決センターのあっせん手続について紛争の当事者を代理すること。
(紛争目的価額は120万円まで)
 男女雇用機会均等法に基づく調停代理
男女雇用機会均等法に基づく調停代理セクハラや労働条件の格差、不利益取扱いによるトラブルが生じた場合、労働者は調停を申請することができ、その調停手続について紛争当事者を代理をすること。
【調停の対象となる紛争】
● 配置・昇進・昇格・教育訓練、福利厚生、職種、定年、解雇等に関する性別による差別的取扱い
● 一定の範囲の間接差別
性別に関係のな事由であっても、運用した結果、男女のどちらかの性が不利益となる場合で、合理的理由のない措置のことで、以下の厚労省令に定めるものをいう。
①労働者の募集・採用にあたって、労働者の身長又は体重を要件とするもの。
②総合職の募集にあたって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること③労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
● 婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱
● セクハラ
● 母性健康管理措置
例えば企業側は、セクハラが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行わなければなりません。
 育児・介護休業法に基づく調停代理
育児・介護休業法に基づく調停代理育児・介護に関する休業制度、休暇制度や労働時間の制限等に関する男女労働者と事業主との紛争に関する調停手続について、紛争当事者を代理すること。
【調停の対象となる紛争】
● 育児・介護休業制度
● 子の看護休暇制度
● 時間外及び深夜業の制限
● 勤務時間の短縮
● 育児休業を理由とする不利益取扱
● 労働者の配置
その他育児・介護休業法の規定に基づく措置
 パート・有期雇用労働法に基づく調停代理
パート・有期雇用労働法に基づく調停代理パート・有期雇用労働法に基づく、差別的取扱い及び通常の労働者への転換への措置義務違反に対する調停手続について紛争当事者を代理をすること。
【調停の対象となる紛争】
● 労働条件の文書交付等
● 待遇の差別的取扱いの禁止
● 教育訓練
● 福利厚生施設の利用機会の配慮
● 通常労働者への転換を推進する為の措置
● 待遇決定についての説明
 労働施策総合推進法に基づく調停代理
労働施策総合推進法に基づく調停代理労働施策総合推進法に基づくパワハラ防止措置義務違反に対する調停手続について紛争当事者を代理をすること。
【調停の対象となる紛争】
●事業主の方針等の明確化と周知
●必要な体制の整備
●パワハラへの迅速かつ適切な対応
●パワハラの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
| あっせん・調停のメリット・デメリット |
【あっせん・調停のメリット】
①原則としてあっせんは1回で終了し、結論が早い。
②和解を前提としており、お互いの合意による解決制度ですので、職場復帰も可能です。
③あっせん申請受理から、特定社労士は代理人として相手側と交渉することができ、早期解決を図る事ができます。
④労働局のあっせん申請は無料です。
⑤あっせん時の合意要件よりも労働審判へ進んでからの合意要件の方が企業にとって厳しくなる傾向にあります。
⑥成立した合意には強制力はありませんが、民法上の和解契約(示談)となり、一方が合意を履行しない場合は、債務不履行により裁判所に訴訟を申し立てる
ことができます。
⑦あっせん又は調停が打ち切られた場合、一定期間内に訴訟を起こすとあっせん又調停の申請時に遡って時効が中断する為、時効の成立を心配せずあっせん又は
調停を利用できます。
【あっせん・調停のデメリット】
この制度は、紛争調整委員会のあっせんによる当事者の自主的合意を前提とした個別的労使紛争解決制度ですから、一方の当事者が、あっせん又は調停の参加を
拒否したり、参加したとしてもあっせん案の受け入れを拒否したりするとあっせん不調となり打ち切りとなります。
| |
|||||||||

|
|||||||||
| |
|||||||||
 |
|||||||||
|
|
|||||||||
Social Insurance And Labor Consulting Office TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com |

 TEL:045-482-6047
TEL:045-482-6047 mail:roumupal@icloud.com
mail:roumupal@icloud.com