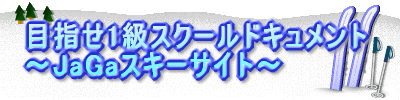
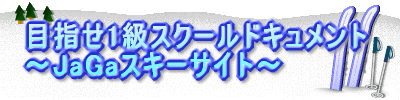
SKI
1.ツェルマットからゴルナーグラート
Ⅰ.スキーパス(SKI PASS = リフト券)のお話
 ツェルマット駅前は箱型の電気タクシーや電気バス、時折馬車などが歩行者とともに行き交い
ツェルマット駅前は箱型の電気タクシーや電気バス、時折馬車などが歩行者とともに行き交い
賑やかでした。電気車による騒音はほとんどありませんから喧騒=人々の休日を楽しむ弾む声
なわけで、聞いてて言葉はわからなくとも心地いいものがあります。
ツェルマットについた人々はそれぞれの宿泊施設へと向かうわけですが、僕らの宿泊地は
ここからさらに登山電車に乗り継いでの標高3千メートルの高地。
ゴルナーグラート・モンテローザ鉄道のツェルマット駅はマッターホルン・ゴッタルド鉄道の
ツェルマット駅とは隣接していて、乗り換えに2分とかからない。
 僕らの利用してきたスイスカードに含まれてる区間はツェルマットまでなので、ゴルナーグラート
僕らの利用してきたスイスカードに含まれてる区間はツェルマットまでなので、ゴルナーグラート
までは新たにチケットが必要だ。さて、ここでスキーパスを購入するか悩んでしまった。
何せ1日に付き7千円相当するのだ。長い旅行の疲労もある、時差ボケは大丈夫そうだが
ここからは高度障害(高山病)も起こり得るかもしれない。「今日滑るとしても1本だけにしよう」
そうちゃまと話し合った結果、スキーパスではなく単独の乗車券を購入することにした。
スイスカードを見せると料金が半額になるというのも大きかった。それでも片道18スイスフラン
約1,800円だ。合わせて明日からのスキーパスを購入することに。
窓口にスウォッチがいくつか飾られてた。これが『200 snow reports』で紹介されてた
スキーパスIC機能を組み合わせたスウォッチか。自分のお土産を兼ねて、マッターホルンの
写真のついた時計に2日分のインターナショナル・スキーパスを組み込んでもらった。
スキーパスにはスイス側だけ通用のスキーパス・ツェルマットと、イタリア側も滑れる
スキーパス・インターナショナルの2種類用意されてる。リフト・ゴンドラ・ロープウェイの他、
登山電車・地下ケーブル・ツェルマット村内のバスとタクシー以外の全ての交通機関に
乗車が可能だ。ざっとその料金を紹介しておこう。クレジットカードは利用可能です。
| 数字単位はスイスフラン(1スイスフラン≒100円前後) | 1Day | 2Day | 3Day | 4Day | 5Day | 6Day | 7Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツェルマット・スキーパス | 67 | 124 | 181 | 234 | 286 | 332 | 374 |
| インターナショナル・スキーパス | 75 | 142 | 204 | 264 | 322 | 374 | 424 |
9歳から16歳までが子供料金となり、約半額となる。それ以下の子供については・・・わかりません。
Ⅱ.雲中雲上のゴルナーグラート・モンテローザ鉄道

話をゴルナーグラート・モンテローザ鉄道に戻そう。車両は新型・旧型の2種類あるものの、
どちらも箱根登山鉄道のような登山鉄道の装い。全車普通席で1等2等の区別はない。
先に乗ってきたマッターホルン・ゴッタルド鉄道の区間区間で見られた3本目のレール
(アプト式レール=ここに車輌の駆動輪を噛み合わせて登り下りする方式)を全区間で
採用してるところに、その険しい勾配を感じさせてくれる。
ツェルマットの標高1,620mからゴルナーグラート3,089mまでの42分の列車の旅はまさに
マッターホルンと共にあると言ってよい。とにかく最初から最後まで、角度や標高差により
その表情を変えながら楽しませてくれるのだ。
マッターホルン・ゴッタルド鉄道に乗ってもマッターホルンはほんの一瞬しか見えないと
お伝えしたが、このゴルナグラート・モンテローザ鉄道に乗ってもスイス最高峰の
モンテローザは 最後ゴルナーグラートの駅でやっとお目にかかれるだけだ。
最後ゴルナーグラートの駅でやっとお目にかかれるだけだ。
こちらをマッターホルン鉄道とネーミングしたいくらいだが、スイスの鉄道名は
終点に到達して見える山の名称をつけてると思えばいいだけの話だ^^
さて、僕らが最初にこの鉄道に乗ったこの日は山の中腹に雲海がたちこめていた。
ツェルマットの村を眼下に次第に高度を上げて8分、最初の駅フィンデルバッハに
着く頃にはもう雲の中に突入。五里霧中何も見えない中を走っていった。
リッフェルアルプ駅からはスキーの格好をした人が板を抱えて乗りこんできたので
この辺はゲレンデと通じてるんだなと想像するくらい。
出発から30分、リッフェルベルグ駅(標高2,500m)に達してもまだ雲の中だ。
ただ車窓から線路と並行するようにスキーヤーが滑ってる。きっとコースが線路と
つかず離れずあるのだろう。
次のローテンボーデン駅に着く直前、いきなりパーッと青空の中に出た。
そう、とうとう雲の上にまで登ってきたのだ。右側の車窓、それはあまりにも非現実的すぎる風景だった。
 眩しすぎる太陽光線、およそスモッグとは無縁そうなすみきった青空、
眩しすぎる太陽光線、およそスモッグとは無縁そうなすみきった青空、
そんな中、美味しそうな雪をたっぷりかぶった、しかしさすがに人を
寄せ付けない威圧さを岩山が表現するアルプスの山々の頂が、
手を伸ばせば届きそうなほんの近くに連なってるのだ。
どの山々も富士山より高い4千メートル級、それが手の届きそうなとこまで
ただ鉄道の席に揺られてるだけで来れてしまう。眼下に広がる雲海の世界、
さらにさらに鉄道は高度を稼いで登っていく。
何とも信じがたい光景ではないか。左側の車窓に目を移すと、
見事に圧雪されたコースを気持ち良さそうにみんなが滑ってる。
いいじゃないいいじゃない! これから過ごす数日間への期待を十二分に
抱かせる光景だ。
雲海を突っ切ってものの数分で終点ゴルナーグラート到着。富士山で
高山病に苦しんだ経験のある僕は、あの恐怖の病状が襲ってこないか
ドキドキしながらの乗車だったが、まずは一安心。ガイドブックには
モンテローザが見えるとあったが、一体どれがその山なのかわからない。
また雲の上に出た筈なのに最後までマッターホルンは見えないままだった。
これがこの日のゴルナーグラート・モンテローザ鉄道乗車記だが、これでは何のガイドにもならないですね^^ 翌日からの
2日間は見事に晴れ渡り、文字通り全線に渡ってマッターホルンを望む車窓からの風景も全く違ったものになりました。
この点についてはこちらで紹介してますのでご覧下さい。
とはいうものの、振りかえって思うにアルプスの自然を痛烈に感じた衝撃と神秘さは、かえって雲海の織り成すこの日の方が
一番でした。ガイドブックには晴れた日に鉄道に乗るよう薦めてますが、雲がかかってる日にも是非乗っていただきたい。
ゴルナーグラートに至ってもなお五里霧中という場合は何の意味もないですけどね。とにかく雲海の上を鉄道が走ってく様は
驚き以外の何ものでもないですよ。
Ⅲ.クルムホテル・ゴルナーグラート http://www.matterhorn-group.ch/de/gornergrat/index.php

標高3,089mのゴルナーグラート駅。その頭上にドーム上の塔を2つ従えた
独特な建築物が立つ。それがクルムホテル・ゴルナーグラート。
世界で最も高いところに建つ本格山岳ホテルなんだそうな。
アクセスは右の写真を見てもらえば一目瞭然。
ゴルナーグラート駅の改札を出たところでスキーをつけて右に進めば
そのままスキーコース。真正面は大氷河を介してアルプスの絶景が
連なる。左側の坂を上がって行くとホテルやストックホルン方面への
ロープウェイ乗り場へと続く。ちなみに写真上部の右側がホテル、
左側の建物がロープウェイの駅だ。
僕らのような旅行の大荷物を抱えた人達は坂道を上がらずとも
エレベーターが用意されている。写真右端のコンクリート枠のところが
乗り場で、これで3階分ほど上がったところがエレベーターの出口、
すなわちホテルの入口だ。
このホテルはほんの数ヶ月前まで休業してて大改装を施したそうだ。
館内に入るとペンキの臭いというか木材の臭いというか、まだ新築の
ようなにおいがとれていない。時計類をはじめとするショップを横目に
 館内を1階上がったカフェのところがチェックイン場所。
館内を1階上がったカフェのところがチェックイン場所。
マッターホルンビューで予約した僕らの部屋は、一つ上の階のちょうど
真ん中の部屋だった。駅の標高からすると、ここはもう3,100mには
なってる筈。部屋は何号室と数字で示されてるのではなく、
山の名前とその標高で記されてるのが不思議だった。
さて、このホテルを予約するにあたっては色んな経緯があった。
今後の旅行者の参考としてそれを記しておかなければなるまい。
『世界一標高の高い本格ホテル』として名を馳せるここは、
もちろん「200 snow reports」にも紹介されてるし、各種のガイドブック
にも登場する。
かつて富士山や白馬などを登山し、山小屋で1泊して山頂からの風景を
楽しんだことのある僕にとっては、3千メートル超の日暮れや朝焼けの
神々しい世界は想像するだけで気分が高揚してくるものであり、
マッターホルンスキーに行く時は絶対ここに泊まろうとはっきり決めて
いたのだ。ホテル側に問い合わせ、まず予約の取れる日を確認し
おさえてから旅程を決めたほどなのだ。ただ20年近く前、富士山で
 高山病に苦しんだ経験があるだけに高度障害がおきないかが
高山病に苦しんだ経験があるだけに高度障害がおきないかが
不安だった。
あの時はまだ若かった。ちょうど7合目あたりで手ぬぐいを巻いた
登山慣れしてそうな50過ぎのおばちゃんに追い抜かれた時、
友達に諌められるのも聞かず負けてたまるかと早足で登っていった。
それが気圧などの変化に対応するにはオーバーペースだったのだろう。
初め身体の節々の痛みや軽い頭痛から始まった症状が次第にひどくなり
8合目から9合目辺りでは吐き気も襲って数歩歩いては数分倒れこむ
という状態になった。日も暮れた頃、予定より2時間以上かかってようやく
山頂小屋に辿り着いたものの、頭痛に腹痛・吐き気・身体の節々の痛み、
およそ人間の病状の全てが襲ってきたような苦しみに唸り悶えた記憶が
ある。翌朝冷たい空気を吸い込んで、日の出と眼下に広がる雲海の
素晴らしさに息を呑み、高山病の苦しみをほんの少し忘れたのも束の間、
陽が昇り雲が切れて次第に感動の風景に慣れてきた頃 またまた
苦しみが襲ってきたのである。
高山病は下山すれば治る=高度を下げなければ治ることがない と
 聞いていたので、砂走りで一気に下りられるルートを選んでほんの
聞いていたので、砂走りで一気に下りられるルートを選んでほんの
2時間ほどで駆け下りた。が、身体の節々の痛みがとれただけで、
頭痛腹痛吐き気はそのままだ。下山口からバスに乗ったものの、ますます
苦しみがひどく、もう我慢できない駄目だ~という時、御殿場駅到着。
その場で一気にもどしてしまった。。。バスから降りたところでよかった。
ところが不思議なもんで、これで今までの苦しみがどこへやら・・・
もどしたらすっかり治ってしまったのだ。
これが僕の富士山登山で経験した高山病だった。
旅程を確定し、イタリアチェルビニアへの大滑降には日本人ガイドさんを
使うことにして、その手配をちゃまに委ねてたところ、そのガイドさんから
送られてきたメールは、高山病経験者の僕にとってはまさに戦慄の
文章だった。
>(前半部分 略)
>それより問題なのは貴方が宿泊する頂上のホテルです。
>このホテルは夏のシーズンに一泊ぐらいする程度で考える場所です。夏季のシーズンと冬季のシーズンとでは
>まったく状況が異なり、そこに冬季に連泊するのは止めたほうがいいですよ。
>良くない理由を知らせます。
>1)時間に制約される、例えば最終電車に乗り遅れると戻れない。
> イタリア側にスキーに行くときは一度1500mの標高差を滑り、ツェルマットの村まで降りてから
> 再度チェルビニア側のロープウエイに乗り継いで3800mまで登り、今度はチェルビニアの村へと
> 滑ります。帰りもまた大変ですよ、それの逆をやるのです。滑る技術と体力があれば何とかなりますが
> ちょっとしたトラブルでゴルナグラードへは戻れなくなります。
>2)標高が高いので(3100m)身体に悪い影響を及ぼす。一晩過ごすだけでも熟睡できない、だるい感じ、
> 頭痛がする、生あくびがでるなどの高度障害の表情が出てくる。にも係らず貴方は3連泊も
> そこに予約してます。せっかくの休暇が台無しと感じるのは私だけでしょうか?
>3)3泊も山の頂上です、少しくらいツェルマットの夕暮れや夜の村中を散歩したりウィンドショッピングなど
> したいと思わないのでしょうか?
> 3100mでの夜は星は綺麗ですが、完全に隔離された世界ですよ。
>4)もし大雪や嵐がきたらホテルから一歩たりとも出れません。登山電車もリフトも全てストップです。
> スキーコースもその場所は標高が高いので閉鎖されたままです。他の所に出かけたくとも
> ホテルの外さえも出れないのです。
> これが最終日で出発しなければならない日や到着日に起るかもしれないのです。
>
>上記したのは決してオーバーな話ではないのです。きわめて普通の事をお知らせしているのです。
>夏季の知識と情報で考えていますので忠告しました。気を悪くしないで下さい。
>そしてもし今からでもホテルを変更可能なら是非ツェルマット村内のホテルに変えるべきです。
>このままでは貴方の大切なスキーバカンスが失敗するのを見ていられません。
>夏と冬はまったく異なりますので勝手に情報誌を鵜呑みにしては駄目です。

現実に高山病を経験してる僕には、高度障害への不安は大きい。現地に住み、マッターホルンの
舞台を職業としてる人の発言は重い。ホテルを変えるべきか・・・とても悩んだ。決め手に
なったのは「今回の旅行の一番の目的は何?」ということだ。ちゃまの長年の夢である
『マッターホルンをこの目で見たい』これに尽きるのだ。富士山で高山病に苦しんだ時も、
あの山頂からのご来光・雲海・天上世界、あれを経験出来たから最高の思い出となった。
今回高度障害を恐れてマッターホルンが見られなかったら、それこそ悔いばかり残る旅行に
なるであろう。悪天候が続いてツェルマットの村からその雄姿が拝めなかったとしても、
ゴルナーグラートなら標高3千メートル超、雲の上に出られるかもしれない。麓で見られなくたって
ゴルナーグラートの方が可能性はあるのだ。結果閉じこめられたとしても、何も出来ない滞在と
なってもマッターホルンに出会えるほうをとりたい!
そんな経緯があって、ガイドさんの忠告にあえて逆らってまでこのホテルにやって来たのだった。
完全改装後の真新しい部屋の居心地は最高。木の香りに包まれ、リネン類調度品その他も
清潔感あふれる。お風呂はないが、シャワーは水流が強く使い勝手がよい。このシャワーも
洗面台もお湯の温度は安定し てて、急に冷たくなったり熱くなったりということはない。
てて、急に冷たくなったり熱くなったりということはない。
トイレの水流も平地のホテルと全く同じだ。改装前は共同シャワー共同トイレだったと聞いてるが、
今はもちろん部屋内についている。ベッド、これがまた最高に気持ちいい。
固めのクッションは疲れを残さず白いふわふわの羽毛のような肌触りのかけ布団は、
ベッドというより布団に包まってるような快適さだった。
これだけの高地にいながら室内空調設備も万全のようで、冷暖に困ることもなかったし、
朝喉をやられることもなかった。
部屋はマッターホルンビューの筈だったが、一体どれがマッターホルンなのかわからない。
山頂が尖ってるそれらしき山はいくつか目に入るものの、よく写真で個性を誇示してるあの独特な
山容は見受けられないのだ。

 そう、実はこの日はマッターホルンは完全に雲に包まれてたらしく
そう、実はこの日はマッターホルンは完全に雲に包まれてたらしく
全く見えなかったのだ。雲海の上に出て辺り一面快晴の山上世界としか
思えなかった風景だが、マッターホルン方向だけは濃霧に包まれてた
ようだ。(それは翌朝、部屋窓の真正面にマッターホルンが姿を現した
ことでわかった)
ついでホテルの食事について。スイス料理と言えば何と言っても
チーズフォンデュ。あまりチーズが得意でない僕にとっては悩みの種
だったが、ありがたいことに2夕食とも出てこなかった。

 前菜・スープ・メイン(2種類からチョイス)・デザートのコーススタイル。
前菜・スープ・メイン(2種類からチョイス)・デザートのコーススタイル。
かといってソースで食べさすフランス料理やオリーブオイルなどで
繊細にアレンジしたイタリア料理ではなく、どちらかというと素材を
どーんと盛り付けてしっかり塩を効かせて食べさせてくれる料理。
間違いなく日本人の口に合う料理です。しかもどれもボリュームたっぷり。
ちゃまなんかコース前半で既に満腹近い状態で、メインは2日間とも
食べきれず残してました。後述するが、僕らはこのホテルのほか、
5つ星のリッフェルアルプリゾートホテルのメインダイニングでも
食事したが、間違いなくクルムホテルの方が美味しかった。
 このホテルならではのダイニングの雰囲気も素敵。ダイニングの窓からは
このホテルならではのダイニングの雰囲気も素敵。ダイニングの窓からは
マッターホルンは見えないものの、スイス最高峰モンテローザをはじめ
リスカム・ブライトホルンなどが正面に聳え立つ。ディナーは19時から
始まるが、こちらで19時というとまだまだ明るく、19時半くらいにようやく
夕焼けが始まる。日没は20時頃。これら4千メートル以上の山々に
囲まれたレストランの大きな窓からは、眼下に広がる雲海・その雲から
太陽光線の反射を受けてオレンジ色に染まるアルプスの連なり。
公害・スモッグとは全く無縁の澄みきった空間が迫りくる迫力に輪をかける。この天上世界にいるのはわずかにこのホテルの住人とスタッフ達だけ
 なのだ。やがて映画のような夕暮れ劇の幕が下りると、テーブルには
なのだ。やがて映画のような夕暮れ劇の幕が下りると、テーブルには
ロウソクがともされ、お洒落で雰囲気あるディナータイムはメイン料理を
迎える。まるで全てが自然なドラマのように進行していくのだ。
キャストを演じる客は2日目も見慣れた顔。小規模な非現実世界では、
仲間達の顔はすぐに覚えてしまう。どのグループ(夫婦)も何故かいつも
同じテーブルをチョイスする。もちろん僕らも。内側に座ってる老夫婦は
ほんとによく飲む。ワインだけではない、リキュール類も次々に
運ばれてくる。飲むといえば他のテーブルの客達もボトルでワインを
あけてる。僕らはというと・・・ダメだった。標高3,100メートルはダテでは
ない。ちゃまが頼んだワインをほんの一口舐めただけでもうぐるぐる
まわってしまった。どちらかというとお酒に強いちゃまも1杯あけられず
半分以上残した。こちらの人の体機能って一体どうなってるんだろうか・・・
驚くしかない!
朝食はバイキング。ちゃまによるとブッフェ方式なんだそうな。そう、僕は
 一度も朝食に行けなかった。もちろんハプニングに襲われたからなのだが、
一度も朝食に行けなかった。もちろんハプニングに襲われたからなのだが、
それはまた後のページで紹介しよう。
館内にあるショップでは、時計・ナイフ類やバックパック(リュック)などを
売ってたが、スキー用品やお土産品などはなし。
ちなみにホテル代は、1泊2食税サ込みで一人あたり150スイスフラン
(マッターホルン・ビュー)、モンテローザ・ビューだと130スイスフランと
決して高くはない。(1スイスフランは100円しないくらい)
このホテルの公式格付けは3つ星。バスタブがないことなどもこの評価に
影響してるのだろう。だがこの施設・雰囲気の素晴らしさはどうだ!
5つ星に引けをとらない、いや、それ以上の感動を間違いなく与えて
くれるだろう。
確かにより標高の高いところに建つ山小屋などの宿泊施設は多い。
何を持って本格ホテルというかは難しいが、「世界で最も高所に建つ
本格ホテル」 このキャッチフレーズに偽りはなかった。
第三章 2.アルプス初滑降 につづく
マッターホルン・スキーパラダイス トップページにもどる
スキー編のページにもどる トップページにもどる