浅 倉 畳 店−伝統の技術
プロローグ−畳が部屋にぴったり収まることの不思議
畳というのはたとえば壁紙や絨毯のように現場に持ってきてから切ったり貼ったりということはできません。
ヘリの着いている側もついていない
ですから寸法を測ることがとても重要なのです。
でも、どのようにして寸法を測るのでしょうか?
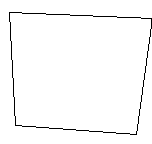
右図と同じ大きさ、形の四角形(長方形ではありません)の図を別の紙に書き写しなさい。
という問題があったとき皆さんならどうするでしょうか?
きっと定規と分度器を持ってきて、まず底辺の長さを測り
つぎに底辺の両端から上方に伸びるそれぞれの線の角度を
分度器で測り、・・・・・・・。
でも分度器がなかったらどうでしょう。部屋にあてがうような大きな分度器なんて見たことないですし。
たとえば物差しと三角定規しかなかったとしたらどうでしょう。
皆さんちょっと考えるのではないでしょうか。
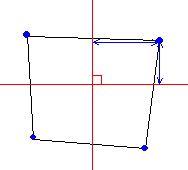
正解はこうです。
まず、四角形の中程に横線を引きます。
次に三角定規を使って横線に対して垂直(直角)になるように縦線を引きます。
次は中学校で習ったグラフで座標の位置を位置をはかるように赤い線から四角形の四つの頂点の位置までの長さを測ります。
そして別の紙に直角に交わる縦線と横線それと四つの頂点の座標点を書き写します。
後は各頂点を線で結ぶだけです。
実は畳の寸法取りもこの要領なのです。
十字本法(大阪本法)
| この方法は上で説明した理屈を使います。 今回は6畳間とします。 まず部屋の基準となる位置 (おおよそ縦の赤線と横の赤線の交差位置) を中心に縦と横に糸を張ります。 この際、縦糸と横糸を直角に交わるようにします。(図1) |
図1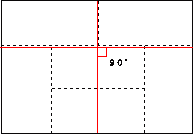 |
| そして、部屋の敷居や畳寄せの基準となる位置 畳寄せに付いた位置とと中間位置(おおよそ縦に3等分した位置) から糸までの長さを測るのです。(横向きの青線の長さ) |
図2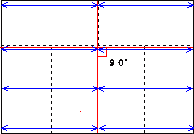 |
| つぎに、部屋の敷居や畳寄せの基準となる位置 畳寄せに付いた位置とと中間位置(おおよそ横に4等分した位置) から糸までの長さを測ります。(縦の青線の長さ) |
図3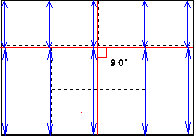 |
最近では直角に交わる赤い線を糸に代わってレーザー光線によって現せる機器が普及してきており、寸取りが大変簡単になってきています
。割本法(東京本法)
| この方法はまず二本の対角線の長さを測り、 その対角線の差をそれぞれの角に振り付ける方法です。 | |
| たとえば、 縦の長さも横の長さも全く同じ四角形があったとします。 仮にこの一辺の長さを2mあったとしましょう。 しかし対角線の長さの差は10mmだったとします。 (通常これだけ差がある場合、正方形に畳を作ると入りません。) (図1) |
図1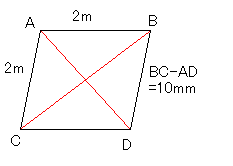 |
| この場合、長い方の対角線の一つの角を 7mm飛び出した形にします。 (縦と横の長さがほぼ同じ場合) 辺の長さは変えられませんから隣の角は7mmひっこめます。 (図2) |
図2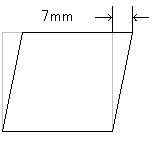 |
つまり10mm対角線に差がある場合は7mmの割で長さを出してやります。
このことを「
さらにここから、それぞれの辺がまっすぐかどうか
曲がりがないかを糸を張って張って調べます。
おおよそこの要領で寸法をとる方法を割本法といいます。
多少誤差はありますが、畳制作については許容範囲です。
掛歪法
| 一見すると長方形に見える部屋も、 実は歪んでいる事があります。 ( 図1のように平行四辺形になっている。 )
|
図1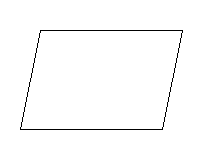 |
| 通常このような部屋に畳を敷くと ( 十字本法で割り振ると ) 図2のようになります。 |
図2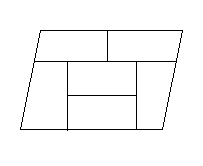 |
| このような割り振りですと最悪の場合、 床材料が寸足らずになることがあります。 (赤色の部分) |
図3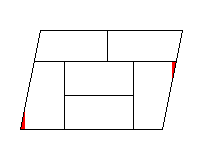 |
| 枕物の畳はこのような形になるのですが、 縫着機などの機械で製作する場合、 誤差が出やすくなります。 ( 機械そのものの特性や刃物の特性によるが 指定した寸法に仕上がらない。 ) |
図4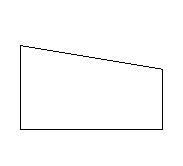 |
| また、 採寸の際、測る位置が少しずれるだけで 仕上げる寸法が変わってしまいます。 |
図5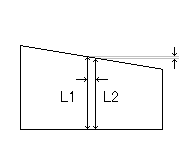 |
| 以上のような事をさけるために、 図6の様にすべての畳一枚一枚に |
図6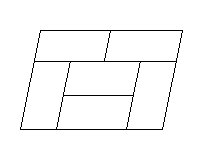 |
このように、すべての畳一枚一枚に曲を割り付ける方法を掛歪法といいます。 このやり方は十字本法よりも割本法と組み合わせるほうがより効率的に長所を生かすことができます。 長所としては
寸取りと制作の際に誤差を小さくできる
枕物の下前の目乗りを乗せやすい
部屋全体の歪みを感じにくく、仕上がりが美しくなる
などがあります。
四一法
畳の寸法取りには常に部屋がどれぐらい歪んでいるかを把握することが重要になってきます。 歪みを測るには直角がわかる方法を知らなければ成りません。 直角といえば良く知られているものに中学校で習った「ピタゴラスの定理」があります。 直角三角形の直角を挟むそれぞれの辺の2乗の和は斜辺の2乗に等しい、というものです。 よくあるのが3:4:5の三角形。それと1:1:√2の三角形です。
ここで話は変わりますが、江戸間の畳の幅は2尺9寸が基準の寸法になっています。直角を挟む辺をそれぞれ2尺9寸と2尺9寸とすると斜辺を4尺1寸とするのです。
29×29=841
841+841=1682
41×41=1681
√1682=41.0121・・・・・
誤差は1厘少々です。